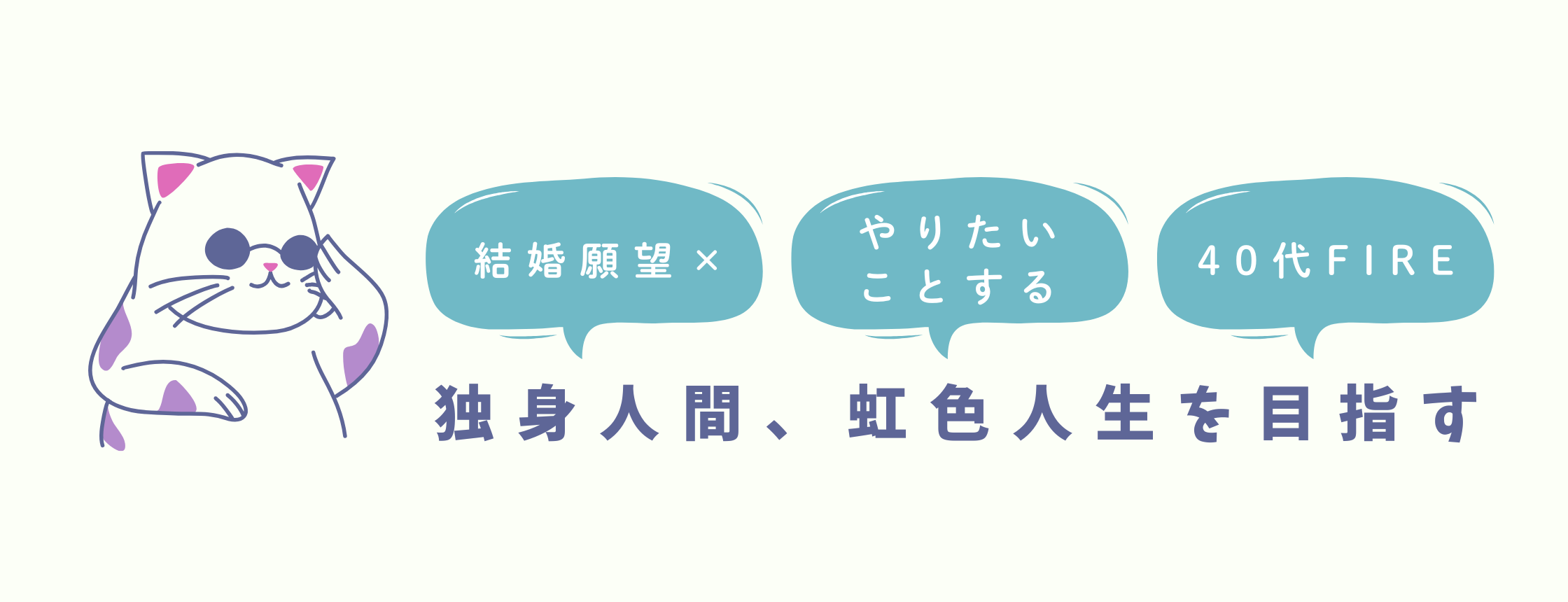貯蓄型保険は「絶対」に入ってはいけない!契約中の人は今すぐ解約すべき理由
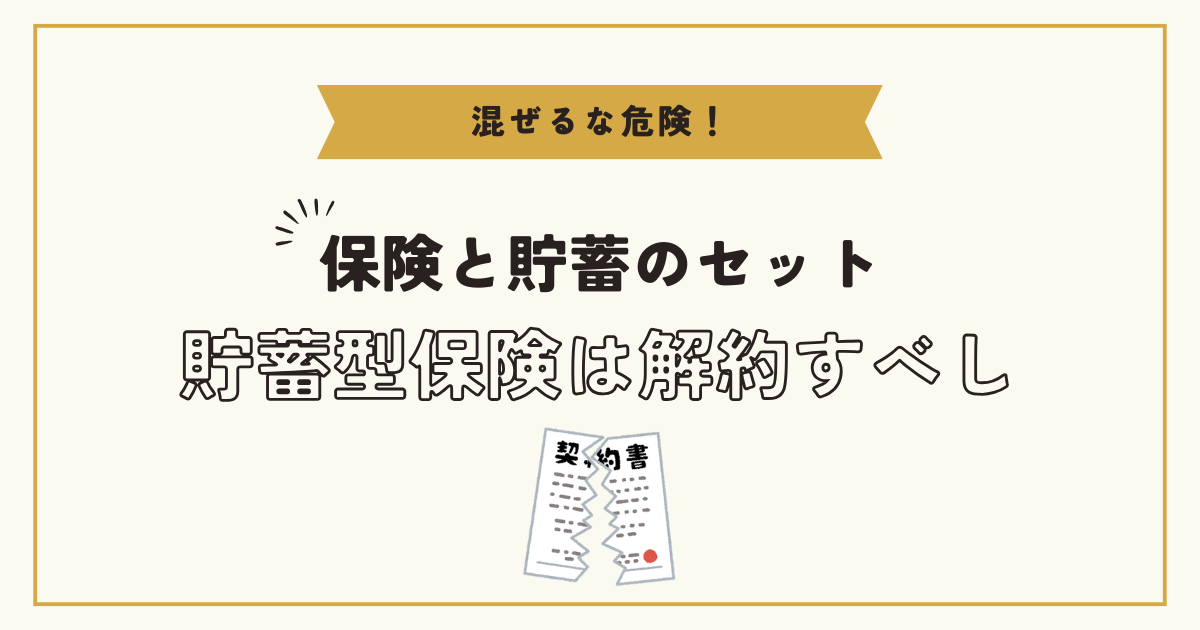
今回は家計や資産形成において、特に多くの方が「よかれと思ってやっているけど、実は損をしている」という非常に重要なテーマを取り上げます。
それが、「貯蓄型保険」と呼ばれる商品です。
- 「貯金代わりになるならいいんじゃない?」
- 「保険と資産形成が同時にできるならお得でしょ?」
- 「営業の人が丁寧に説明してくれて、よさそうだったから…」
そう思って契約していませんか?
もしあなたがそうであれば――今すぐにこの記事を最後まで読んでください。
そして必要であれば、保険証券をすぐに引っ張り出して「解約」という選択肢に真剣に向き合ってみてください。

まずは結論から。
貯蓄型保険は、あなたのお金を「じわじわ奪っていく」商品です。
しかも、多くの人はそのことに気づかないまま、数十年もの投資機会を無駄にしています。
今回は、そんな貯蓄型保険の「本当の姿」を徹底的に掘り下げていきます。
そもそも「貯蓄型保険」とはどんな保険?
まずは言葉の定義から整理します。
「貯蓄型保険」とは、簡単に言えば将来に一定額の返戻金(へんれいきん)が戻ってくるタイプの保険のことを指します。
代表的なものとして、以下のような保険商品が挙げられます。
- 終身保険(貯蓄型)
- 学資保険
- 養老保険
- 個人年金保険
- 外貨建て生命保険
- 変額保険
保険といえば「万が一のときに備える」ものというイメージがあると思いますが、貯蓄型保険はそれに「お金が戻ってくる」という特徴を加えた商品です。
「どうせ保険料を払うなら、掛け捨てより、貯金になる方がいいよね」
そんな心理を巧みに利用して作られた商品。
それが貯蓄型保険です。
【危険①】利回りがあまりにも低すぎる
ここからは、なぜ貯蓄型保険が損なのか、具体的に見ていきましょう。
まず1つ目の理由は、「利回り(=お金が増える効率)が非常に低い」という点です。
たとえば、30歳の人が月2万円の終身保険に加入し、30年間払い続けたとします。
総支払額は「2万円 × 12ヶ月 × 30年 = 720万円」
この人が60歳になった時点で受け取れる解約返戻金(あるいは満期返戻金)はいくらになるでしょうか?
多くのケースで、750万円〜800万円程度です。
つまり、30年間もお金を預けた結果、利益はたったの30万円〜80万円。
年利に直すと0.5〜1.2%程度です。
【比較】投資信託や積立NISAだったらどうか?
同じ金額を「全世界株式インデックスファンド(年利4%想定)」で積み立てていたら、30年後にはいくらになるか。
答えは約1400万円です。
つまり、同じお金を貯蓄型保険に預けるか、投資信託に預けるかで、最終的な資産が2倍近く変わるのです。
【危険②】途中で解約すると、大損する
これが非常に多くの人がハマる落とし穴です。
貯蓄型保険の特徴として、「契約から数年間は、解約してもほとんどお金が戻らない」という重大な欠点があります。
実際に保険証券や返戻金表を見てみてください。
契約から3〜5年程度の返戻率は、50〜60%台です。
つまり、100万円払っても、60万円しか戻らない、というような状況が普通に起こり得ます。
結婚・転職・住宅購入・出産・病気・介護など、人生には「想定外」の出費がつきものです。
そんなとき、すぐに引き出せるお金を持っていないと、生活そのものが不安定になります。
でも、貯蓄型保険に預けているお金は「自由に引き出せない」んです。
【危険③】保険と貯蓄を「ひとつにまとめる」ことのリスク
そもそも「保険」と「貯蓄」は、まったく別の目的のものです。
- 保険は、万が一のリスクに備えるもの(保障)
- 貯蓄・投資は、将来の生活や目標のためにお金を増やすもの(資産形成)
この二つをひとつの金融商品にまとめるというのは、一見便利そうに見えて、実はものすごく非効率です。
保険機能が必要なくなったときも、資産運用の方針を変えたいときも、柔軟に動くことができません。
【危険④】手数料のカラクリに騙されている
「どうしてこんなに条件の悪い商品を保険会社は販売するのか?」
その答えは、販売手数料にあります。
貯蓄型保険は、保険会社や代理店、営業担当者にとって、非常に利益率が高い商品なのです。

例えば、ある保険会社の営業マンがあなたに終身保険を売った場合、契約初年度に支払保険料の30〜50%を手数料として受け取るというケースもあります。
つまりあなたが月2万円の終身保険に加入したら、営業マンには初年度で10万円以上の報酬が入るということになります。
これが、貯蓄型保険が積極的に勧められる「裏の理由」です。
【よくある誤解と反論への答え】
Q「元本保証なら安心でしょ?」
【A】
元本が戻るまでには20年、30年とかかりますし、その間に本来得られたはずの運用益はすべて失われています。
しかもインフレが進めば、将来戻ってきたお金の「実質価値」は今よりずっと下がっています。
Q「銀行に預けるよりはマシなのでは?」
【A】
確かに、普通預金の金利0.001%よりは高いです。
しかし現在は、積立NISAやiDeCoなど、税制優遇のある投資制度を活用すれば、年利3〜5%も現実的に狙えます。
銀行と比較しても意味はありません。
Q「親が勧めてくれたので…」
【A】
親世代の金融常識と、現代の金融環境はまったく異なります。
彼らの時代には貯蓄型保険も悪くなかったかもしれませんが、今の超低金利時代には完全に「時代遅れ」の選択肢です。
すでに加入してしまった人が取るべき行動
- 解約返戻金はいくらか?
- 払込期間は何年あるか?
- 保険料総額はいくらになるか?
これらを確認するだけでも、自分がどれだけ損をするか、今後どれだけ縛られるかが見えてきます。
たとえば、総支払額600万円、解約返戻金が400万円だとしたら、今解約すると200万円の損になります。
「え?そんなに損するなら、続けた方が得じゃない?」
そんなふうに思うかもしれません。
しかし大切なのは、今から先に支払う分に対して「それが合理的に見合うか」を判断することです。
これから10年かけて400万円払って、解約時に420万円しか戻らないなら…もうやめた方がいいですよね?
- 必要な保険だけ、「掛け捨て型」でシンプルに加入する
- 死亡保障・医療保障 など
- 浮いた保険料を、資産形成に回す
- 積立NISA、iDeCo、高配当株、債券ファンド など
- 将来必要なお金を、自分でしっかり運用して作っていく
- 教育費・老後資金 など
まとめ
保険は「リスク対策」、貯蓄は「自己責任の資産形成」
保険は「リスクに備える」ためのものであって、「お金を増やす」ためのものではありません。
資産形成をしたいなら自分で投資を学び、必要な制度を活用する。
それが今の時代にふさわしい賢いお金の使い方です。
そして何より、貯蓄型保険という商品にこれ以上騙されないためにも、「知らないことは損すること」だという事実を、今ここで強く自覚しましょう。
最後に
- 「昔、保険に加入したまま放置してるな…」
- 「何となくいいと思って入ってたけど、本当に得なの?」
- 「このまま老後まで払い続けていいのかな…」
そんな不安が1ミリでもあるなら、今が見直しのチャンスです。

この記事を読んだ「今日」という日を、お金の使い方を改める人生のターニングポイントにしてください。